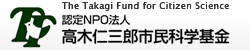リサイクルをめぐる物質の流れの実態調査とその評価
| 桑垣 豊 さん | ||
| 50万円 |

大誠樹脂
研究の概要
リサイクルをめぐる物質の流れについてプラスチック等を事例として実態調査を行い、リサイクル方法の評価や政策提言を試みます。
中間報告
中間報告から
<進行状況>
◆廃食用油リサイクル
見学 ロンフォード(滋賀県) 廃食用油からバイオディーゼル油を生産している工場
資料収集 「我が国の油脂事情」など基本データの収集
成果 油の種類ごとの生産から消費までのフロー図の作成
30品目、10年分
最近20年間の廃食用油発生量の推定
滋賀県庁で上記の内容を報告
◆プラスチックリサイクル
見学 ヨネプラ見学(大阪市)
大誠樹脂見学(埼玉県、東京都)
資料収集 「プラスチック製品統計」など基本データの収集
成果 プラスチックの生産から廃棄までのフロー図の修正
「プラスチックはリサイクルするべきか」月刊社会運動2002/8掲載
<今後の予定・課題>
◆廃食用油リサイクル
見学 廃食用油を減量とした工場の見学(せっけん、飼料、印刷関係)
植物油の製造メーカー見学
回収業者へのインタビュー
業界団体へのヒアリング
資料整理 基本データを25年分に拡張。様々な経年データを分析。
課題 廃棄後のデータが少ないので業界団体への聞き込みなどから推定方法をさぐる
リサイクルの使い道(せっけん、燃料、飼料、印刷など)ごとの評価
消費段階での節約、油摂取過剰問題の評価
家庭などから排水への流出による水汚染の評価
◆プラスチックリサイクル
見学 塩ビリサイクル工場
自治体「その他プラスチック容器包装」資源化施設
高炉還元、油化、燃料化施設
資料整理 樹脂の種類ごとのデータ整理
課題 プラスチックがリサイクルできる条件が厳しいことを明かにして使用量削減の必要性を証明
塩ビリサイクルの問題点の洗い出し、整理
「容器包装リサイクル法」の「その他プラスチック容器包装」リサイクルの問題点の整理
結果・成果
完了報告から
リサイクル全体の中での位置付け
今回は調査の対象からはずしたが、コンクリートとプラスチック、廃食用油のリサイクルを比べてみます。
まず、寿命の違いから蓄積の問題が生じます。プラスチックはコンクリートの50年という寿命に比べると、数分の1しか寿命がないが、方向転換がむずかしいことを考える必要があります。プラスチックでは、当面使い捨てが問題ですが、長期的には耐久品の大量廃棄を未来にひかえています。
廃食用油は、蓄積することはあまりなく、その点、アルミ缶などの使い捨て品と同様です。しかし、生物が原料で劣化することや、人間が摂取するものである点が大きく異なります。
廃食用油とプラスチックは、その種類が多様で、その組み合わせまで考えると非常に複雑です。その点では、アルミ缶やコンクリートにはない問題があります。
プラスチックでは、塩ビとそれ以外で様々な面で事情が異なっています。廃食用油でも、動物油と植物油で事情はことなり、それぞれ採取する生物の種類によって性質が変わってきます。今回、植物油の種類まで調査がおよびませんでしたが、今後の課題です。
有害性
プラスチックはその添加剤や焼却時のダイオキシン発生など、有害物質の発生源になりうるという意味で有害性が課題となります。
一方、廃食用油では、外部から有害物質が混入するかどうかが問題となります。もちろん、どのようなリサイクルでも、不純物の混入をいかに排除するかが永遠の課題です。
廃食用油はそれ自身有毒でないが、水系に流せば有害です。リサイクルでは資源節約の面が注目をあびがちですが、環境中に有害なものを出さないという面が重要です。特に有害でなくても、埋立地を枯渇させるごみ問題からはのがれられません。
政策提言
当たり前ながらリサイクルを等身大で評価するべきですが、全面否定か全面肯定になりやすい。リサイクル問題はこのような原則論が通用せず、個別性が強いのです。
政策提言として、調査にもとづいて大きな原則をうちだすことは、リサイクル問題の性質上むずかしい。一般論として、拡大生産者責任や、有価物かどうかで廃棄物になったり資源になったりする規定を改める必要性などが議論の対象になります。
しかし、その原則はある意味当然のことであり、そこから出発して個別リサイクルでどう対応するべきかを検討しなければなりません。今回の調査は、その前提となる事実の解明に中心をおいているので、大々的な政策提言はできませんが、以下列挙します。
1)プラスチック
・生産量全体の抑制が必要 リサイクルでは対応できない場合が多い。
・塩ビは特別あつかい 塩ビなど塩素を含むプラスチックは別に考える必要がある。
・耐久品を中心とした使い道に重心を置くべき
・リサイクルしやすい設計を 寿命の長さを考え解体しやすい設計をさらに促進、ごみ輸送コストもさげる
・圧縮施設の建設はやめる 容器包装リサイクル法の「その他プラスチック」は回収しない
2)廃食用油
・水汚染対策の側面が重要 水汚染対策としての位置付けが必要
・原料輸入による自然破壊 パームなど東南アジアの自然と農業への影響を考える
・技術開発の促進 せっけん製造、レストランなどでの回収システム、肥料化、燃料化で開発の余地
・油の使いきり推進 油こし器の市場などが未成熟、安物の油は使い回しができず割高などの知識普及
・油脂の過剰摂取問題 健康問題とともに廃棄量を増やすことにつながっている
その他/備考