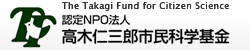原発労働者の労働安全・補償制度と被曝労働災害の実態に関する国際調査
| 被ばく労働を考えるネットワーク |
研究成果発表会配布資料[pdf] |
|
| 渡辺 美紀子 さん | ||
| http://hibakurodo.net/ | ||
| 100万円 |

釜山で開催した福島原発事故と労働者被ばくに関する報告・討論会の様子(2017年5月24日)

釜山での情報交換と打ち合わせ(2017年5月24日)

民主労総金属労組蔚山支部との情報・意見交換と交流(2017年5月25日)
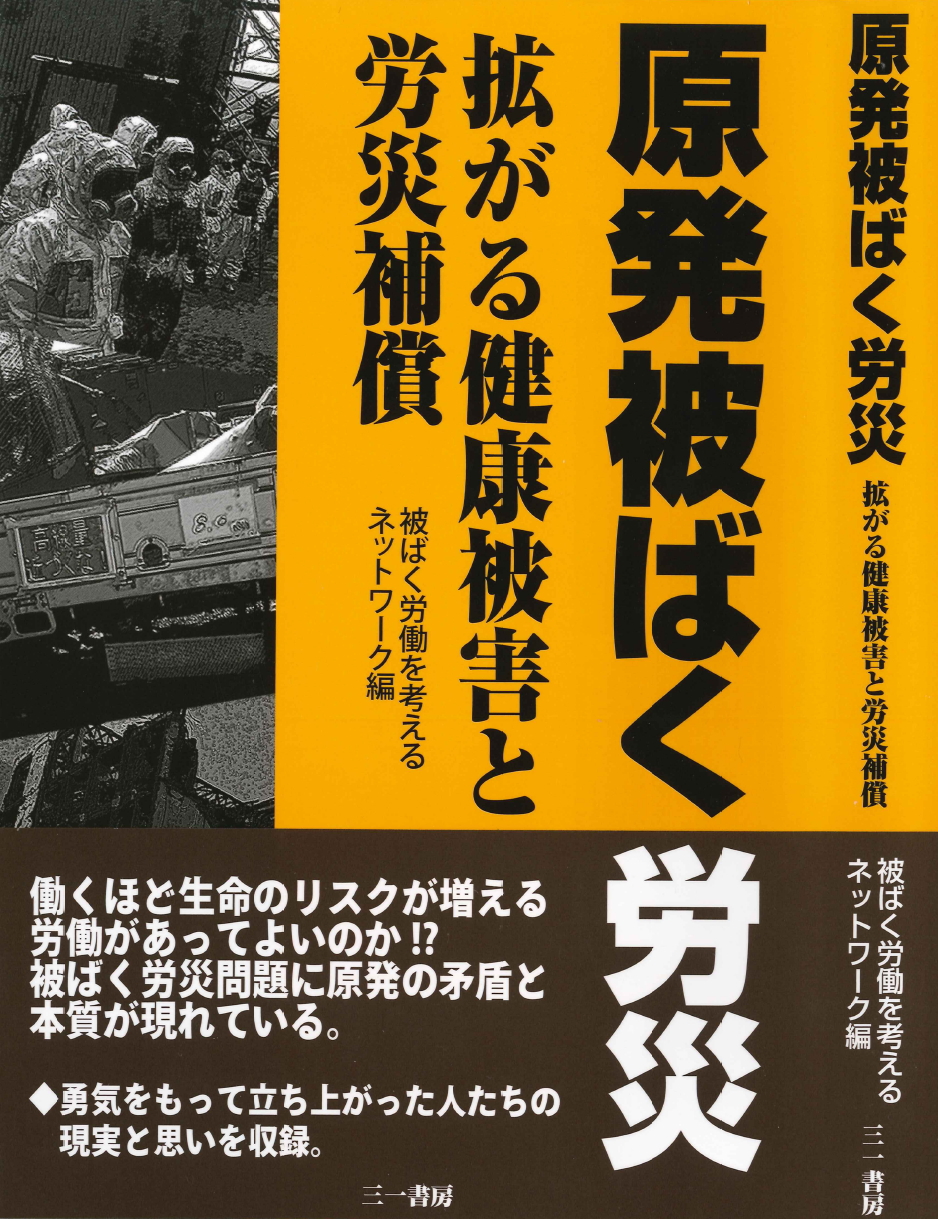
被ばく労働を考えるネットワーク編『原発被ばく労災─拡がる健康被害と労災補償─』、三一書房、2018年6月5日発行
研究の概要
2016年12月の助成申込書から
福島原発事故以前から政府と電力会社及び元請会社は、原発労働者の労働実態と健康被害状況について、隠蔽と言って差し支えないほど明らかにしていない。その条件のもとで、主として非正規雇用労働者が使い捨てられてきた。労働者保護制度は不備であり、使いうる制度さえ労働者がアクセスしにくい環境が作られている。被曝労災・労災死を一人でも減らすため、原発被曝労働に関する実態解明、労働安全・労働者保護制度そのものと運用のあり方の抜本的見直しは緊急の課題である。また、原発問題のアキレス腱でもある被曝労働問題があまり注視されないのは、原発を持つ他の国でも同様であり、この問題は国際的な共通課題である。
本研究では、日本のみならず原発を有する各国について、公開資料等から原発労働者の労働安全制度と労災補償制度について比較するとともに、各国の労働団体・市民団体と協力して労働者への聞き取り調査を行い、労働実態と労災・健康被害の国別比較を行い、そこから捉えうる問題を明らかにすることを目的とする。
研究を進める国内体制としては、被曝労働問題に取り組む諸団体や社会学的調査の経験がある研究者と共同で行う。国際的体制としては、2016年3月に開催された「核と被ばくをなくす世界社会フォーラム2016」に参加したウクライナ、フランス、ドイツ、韓国、日本のメンバーの協力共同で進める。
この成果は、労働者や市民に対して被曝労働に関する正確な情報を提供するために用いるとともに、各国政府および事業者に対して、労働安全・労働者保護制度の改善を要求するために用いる。
中間報告
2017年10月の中間報告から
原発労働者の労働実態と健康被害状況は、隠蔽されていると言えるほど情報が明らかにされておらず、主に非正規雇用労働者が使い捨てられてきました。原発被ばく労働に関する実態解明と労働安全・労働者保護制度の問題は、深刻な被ばくが懸念される事故収束・廃炉労働者の命と健康を守るために喫緊の課題であるとともに、原発再稼働をめぐるアキレス腱でもあります。また、被ばく労働問題があまり注視されないのは、原発を持つ他の国でも同様であり、国際的な共通課題です。
本研究は、日本、ウクライナ、フランス、ドイツ、韓国などにおける、原発労働者の労働安全制度と労災補償制度について比較するとともに、各国の労働団体・市民団体と協力して労働者への聞き取り調査を行い、労働実態と労災・健康被害、制度運用のあり様について国別比較を行います。そこから抽出される共通点と国ごとの特殊性を明らかにし、労働者の立ち位置から取り組む課題を提示します。
日本における被ばくをめぐる労働諸法と労災・補償制度については、現在、資料をまとめたところです。これを海外の共同研究者と共有して、同一項目での調査研究を進める予定です。
5月には韓国(釜山、蔚山(ウルサン))において現地の共同研究者・労働団体・市民団体と情報交換と聞き取りを行いました。この訪問に先立ち、韓国の共同研究者と労組との協力によるアンケート調査が行われており、その集約情報を共有しました。韓国では被ばく労働問題への関心が急激に高まりつつありますが、緊急作業では任命された作業員本人の同意が法的に規定されていないといった問題も明らかになってきました。ドイツとアメリカからも、関連する資料が寄せられており、現在これらの整理を進めています。
10月には調査研究メンバーのウクライナへの訪問を予定しています。11月初旬には、フランスで開催される反核社会フォーラムに参加して情報交換を行うとともに、フランスの共同研究者と共同での聞き取り調査を予定しています。また12月には海外の共同研究者も若干名日本に招き、調査資料をもとにした討論ミーティングを計画しています。
結果・成果
完了報告・研究成果発表会資料より
本研究は、原発労働者の労働安全制度と労災補償制度、および労働実態と労災・健康被害、制度運用のあり様について、国際比較を行うものです。そこから共通点と国ごとの特殊性を明らかにし、取り組むべき課題を提示します。本研究の期間は3年を想定し、2017年度はその初年度でした。
2017年度は、主に日本と韓国、フランスについての調査を進めました。まず、日本における労働諸法と労災・補償制度についてまとめ、これを海外の共同研究者と共有し、同一項目での調査研究を進めることとしました。労働実態については、これまで行われた労働相談などのデータについて、本研究項目に即して整理を進めました。
2017年5月には韓国において現地調査を行いました。原発に勤務する非正規労働者のうち相当数が原発立地地域出身であることや、雇用不安と正規労働者に大きく劣る労働条件などの問題のほか、原発の安全性と放射線防護、安全教育の不足に対する労働者の不安が大きいことが明らかとなりました。
11月にはフランスを訪問し、元労組関係者や原発労働者、研究者などへの聞き取り調査を行いました。雇用形態は日本と同様に重層下請構造(末端は5 次下請程度)で、被曝量の80%は下請労働者が引き受けていました。一方、労災認定や損害賠償では、取り扱いが日本とは大きく異なりました。
被曝による職業病リストにある疾病になった場合、核サイトにいたことの証明があれば、被曝線量に関わらず労災が認められます。また、その労災認定が行われていれば、損害賠償では業務と疾病の因果関係は争われません。これらは日本の労災認定と損害賠償の現在の問題に対して、改善例になり得ると考えられます。
なお、被ばく労働を考えるネットワークは2018年6月に『原発被ばく労災─拡がる健康被害と労災補償─』を刊行し、本研究の成果の一部もまとめられています。
その他/備考