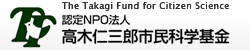水俣市の廃棄物最終処分場建設予定地周辺の地質に関する調査研究
| 水俣病センター相思社 |
2007年度完了報告[pdf27kb] |
|
| 遠藤 邦夫 さん | ||
| http://www.soshisha.org | ||
| 40万円 |

2007-06-03 地質調査 火砕流堆積物の層を調査する

2007-06-05 3万通の意見書を閉じたシャッター越しに受け取るIWD

2007-07-06 産廃県庁行動
研究の概要
2006年12月の助成申込書から
本研究のねらいは、産廃処分場建設予定地周辺およびその下流域における環境について調査し、市民の立場から、処分場建設がもたらす自然環境への影響を正しく予測することである。
水俣市の水源である湯出川の上流に、民間の廃棄物処理業者により204万?という日本最大規模の管理型産業廃棄物最終処分場の建設が計画されている。
市民の間からは、飲み水の汚染や水源の枯渇、工事による斜面の崩落、トラックによる騒音・振動被害、煤塵の飛散による大気汚染、農海産物の汚染等、に対する不安の声が上がっている。
現在、熊本県の条例による環境影響評価の準備書手続きが進行中である。
業者は当初2006年度中に準備書を提出すると述べていたが、その後、二転三転し、2006年12月10日現在、未だ提出されていない。
引き続き調査を進め、処分場の危険性を科学的に明らかにし、業者に処分場の断念を求めていきたい。
2006年2月の水俣市長選挙で産廃反対の候補が当選したが、その後も水俣市の動きは活発とは言えず、市民が独自でデータ収集を行う必要性は減じていない。
2006年度には高木基金より助成をいただいて河川の水質分析および地下水に関連して地質についての学習会等を行った。
2007年度はこれらを踏まえて詳細な地質調査を行う予定である。
中間報告
2007年9月の中間報告から
水俣市の水源地に、民間の産廃業者(株)IWD東亜熊本が管理型産業廃棄物最終処分場の建設を計画している。
事業者は2007年2月に環境影響評価の準備書を提出し、3月に説明会を実施したが、湧水についての住民側の質問に答えることができなかった。
そのため5月に再度説明会を開催したが、十分な説明を行わないまま、強引に説明を打ち切った。
現地は台地上の地形であり、事業者はその上に積み上げる様な形で処分場を計画している。
その下の斜面には多数の湧水が存在し生活用水に使用している。
周辺では土砂災害も発生し、事業実施区域内に断層が存在するなどの危険が存在するにもかかわらず、事業者は「地下水ではなく表流水」「地質構造上、土砂災害の危険性はない」「古い断層で危険はない」などと決めつけている。
そこで私たちは、処分場の危険性を科学的に明らかにするために、今年度は専門家(地元高校教諭)の指導のもと、地質調査を行うこととした。
前期は、4月に学習会、6月、7月に現地踏査を行い、それぞれ簡単な地質断面図とフォトマップにまとめた。
その結果、事業者の地質図に記載されていない地層が発見されるとともに、地質の基本的な把握の仕方が間違っていることが分かった。
すなわち、事業者の地質図においては、地層が一様に西方向に10度傾いているように記載されており、これが事業者が東側斜面には湧水がないと主張する根拠となっているが、実際の地層は火山活動によって起伏ができ、複雑に重なりあっていることがわかった。
また、地層を調査するには表面を覆っているコケなどを削り取って地層が見えるようにしなければならないが、事業者がここ1、2年の間に調査を行った痕跡がないことも分かった。
また、同時に5月の説明会打ち切り以後、水俣市も水俣出身の長谷義隆元熊本大学教授(地質学)に依頼して本格的な地質調査を実施した。
その結果、地質においては現時点では十分な調査データは得られたと考えている。
すなわち、事業者のものとはまったく異なる地質図が描き出され、大森の湧水も昨年の水質調査とあわせて処分場計画地の台地に胚胎する地下水であり、現地は基本的に崩壊地形であることが確認された。
なお、地質調査と平行して、産廃阻止!水俣市民会議と協力し、搬入道路の交通量調査、水生昆虫調査、希少動物調査(カジカガエル、クマタカ等)を行っている。
結果・成果
2008年4月の完了報告から
水俣市の水源地に、民間の産廃業者(株)IWD東亜熊本が管理型産業廃棄物最終処分場の建設を計画している問題で、事業者は2007年2月に環境影響評価の準備書を提出した。
現地は台地上の地形であり、事業者はその上に積み上げる様な形で処分場を計画している。
その下の斜面には多数の湧水が存在し生活用水に使用されている。
周辺では土砂災害も発生し、事業実施区域内に断層が存在するなどの危険が存在するにもかかわらず、準備書では「地下水ではなく表流水」「地質構造上、土砂災害の危険性はない」「古い断層で危険はない」などと決めつけている。
処分場の危険性を科学的に明らかにするために、今年度は専門家の指導のもと、学習会と現地踏査を行い、地層の走向傾斜を測定し、地質断面図とフォトマップにまとめた。
その結果、事業者の地質図に記載されていない地層が発見されるとともに、地質の基本的な把握の仕方が間違っていることが分かった。
事業者の地質図においては、予定地の地層が一様に西方向に10度傾いているように記載されており、これが事業者が東側斜面には湧水がないと主張する根拠となっているが、実際の地層は火山活動によって起伏ができ、複雑に重なりあっていることがわかった。
それとともに、昨年から行っている水質水量調査の結果と合わせて大森の湧水も処分場計画地の台地に胚胎する地下水であることが総合的に証明された。
地質調査と平行して、産廃阻止!水俣市民会議と協力し、搬入道路の交通量調査、水生昆虫調査、希少動物調査(カジカガエル、クマタカ等)、気象の調査を行っている。
絶滅危惧種のクマタカの調査は、地元在住の、日本野鳥の会メンバーの協力をいただき、約半年間をかけて行い、現在も調査を継続している。
気象については、気象庁の中田隆一先生の指導を受け、焼却灰の飛散する様子や、接地逆転層の生成状況などを観察した。
また、4月に風速計を3基設置し、今後、1年間の定点観測を行う予定であり、今後も詳細データの収集・分析を通して、汚染物質の影響を明らかにしていく。
調査の結果は、説明会での事業者への質問や、住民意見書に反映され、水俣市長意見にも取り入れられている。
また、1月の熊本県公聴会でも各方面にわたって調査結果に基づいた科学的な公述が数多くなされた。
その結果、アセスメント審査会では事業者の杜撰な調査に対して厳しい指摘が続出し、3月に熊本県知事からIWD東亜熊本に出された知事意見では、ほとんど全調査項目にわたって、調査や評価のやり直しが求められている。
このことは、私たちの活動の大きな成果と言える。
その他/備考