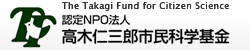高レベル放射性廃棄物地層処分の批判的検討
| 地層処分問題研究グループ | ||
| 伴 英幸 さん | ||
| http://www.geodispo.org/ | ||
| 200万円 |
研究の概要
原子力発電所から排出される高レベル放射性廃棄物の地層処分問題を、核燃料サイクル開発機構の技術報告書『第2次とりまとめ』批判をおこない、高レベル放射性廃棄物の処分問題について広く一般に開かれた議論を起こそうと訴えます。
【 この助成先は、2003年度にも同様のテーマで助成を受けています → 2003年度の助成事例 】
【 この助成先は、2004年度にも同様のテーマで助成を受けています → 2004年度の助成事例 】
中間報告
中間報告から
2002年4月〜2003年3月
基盤的な活動
・グループの定例研究会を14回開催
・廃棄物処分およびバックエンド関係の研究会
・ワークショップ・施設見学等に14回参加
・廃棄物処分関連の政府委員会を24回傍聴
2002年6月 原子力安全委員会特定放射性廃棄物処分安全調査会主催の第2回HLW安全調査ワークショップに石橋がパネリストとして参加
2002年7月 原子力安全委員会特定放射性廃棄物処分安全調査会「概要調査地区選定段階における環境要件の考え方について」報告書(案)へ要望書を提出
2002年9月 公開討論「どうする高レベル放射性廃棄物」企画。
石橋・藤村がパネリストとして参加(資源エネルギー庁および他の市民団体と3月から準備)
2002年9月 パンフレット「埋め捨てにしていいの?原発のゴミ」刊行
2002年12月 地層処分実施主体の原子力発電環境整備機構が処分地の公募を開始
2003年2月 グループのホームページを開設http://www.geodispo.org/(「高レベル放射性廃棄物処分候補地の公募開始にあたって」など)
現 在
・「反論」レポート準備中
・ワークショップ「本音で語る原子力政策」(仮題)を準備中
結果・成果
完了報告から
地層処分関連の多くの研究会・シンポジウム等に参加および政府委員会の傍聴をし、処分技術の現状を把握するとともに、推進側の研究者・技術者と広く討論をする機会を得ました。
現在、日本の地層処分政策は、形式の上では、核燃料サイクル開発機構による技術報告書「わが国における地層処分の技術的信頼性−地層処分研究開発第2次取りまとめ」(1999年)によって、「技術的信頼性」が示され、これを「事業化への拠り所」として進められていることになっています。
当グループは、この「第2次取りまとめ」報告書の技術的な検討から、地層処分によって原子力発電の高レベル放射性廃棄物問題が解決したかのように原子力政策を進めることは誤っており、国が評価したように「地層処分の技術的信頼性が示された」とは言えないとこれまで主張してきました。
あらたに推進側の研究者・技術者と討論を重ね、当グループの考えは推進側から見ても説得力を持つものであることを確信しました。
助成に支えられた活動を通して、「第2次取りまとめ」および処分技術の現状には、2000年に当グループが発表した「『高レベル放射性廃棄物地層処分の技術的信頼性』批判」レポートで取り上げた以外にも多くの問題があることもわかってきました。
そのなかには「第2次取りまとめ」では単純に結論を出しておき、関係者もその問題に言及せずにおきながら、処分事業が進みだしてから課題として触れられはじめた問題もあります。
たとえば、「第2次取りまとめ」では、火山の分布はいわゆる「火山フロント」によって説明され、第四紀火山の近くでなければ処分場への火山の影響は避けられるとしているが、こうした議論が当てはまるのは東北日本と九州南部だけで、単成火山群(主に中国地方と九州北部)は活動域が広く、新しい地点で活動が始まるという特徴をもっており、処分場の適地が日本中に広く存在するという「第2次取りまとめ」の結論は乱暴にすぎます。
また、処分坑道の支保工に使われるコンクリートには、ガラス固化体を収納する金属容器の腐食や粘土の緩衝材の性質に影響を及ぼさないという観点から、「第2次取りまとめ」では低アルカリ性コンクリートを使うことが前提とされており、その施工性も確認されたという記述があるが、これも実はまだ技術開発の途上段階にすぎません。
この他にも、放射性物質がガラス固化体から溶け出したあと、人間の生活圏に達するまでの核種移行のコンピュータープログラムを作成することで、2000年の「批判」レポートより具体的に、「第2次取りまとめ」のモデルの問題点や課題を明らかにしました。
このように、「第2次取りまとめ」に代表される現状の処分技術は「地層処分の安全性」を確信させるには遠く、あたかも「地層処分の安全性」が確立しているかのようにして進められている現在の処分政策を改める必要をふたたび世に問うべく、新たな知見や成果をもとに、核燃料サイクル開発機構による「見解」レポートに対する再反論のレポートを現在作成中です。
このように技術的な問題に正面に取り組んだ批判の一方で、技術的な詳細に立ち入りすぎることなく地層処分の問題点を伝えるため、本基金の助成を受けて、A4判カラー12ページのパンフレット「埋め捨てにしていいの?原発のゴミ」を2002年9月に刊行しました。
イラストを中心にした構成をとったうえで、読み応えのある解説のページを設けました。
10,000部作成し、これまでに約4,000部がさまざまなかたちで世に出ています。
各地の運動や個人の方から、まとまった部数の依頼があり、好評を得ています。
現在、処分事業は原子力発電環境整備機構が候補地を公募で募っている段階で、これに応じて同機構からさまざまな説明資料が発表され始めています。
グループではこれらの資料も検討しており、その問題点を指摘していく予定です。
2002年9月には資源エネルギー庁主催の「放射性廃棄物シンポジウム2002」を同庁と、核のゴミキャンペーン・高木学校・原子力資料情報室の共同企画で、公開討論「どうする高レベル放射性廃棄物」として開きました。
開催にこぎつけるにあたって多くの困難があり、準備の会合を通して多くのことを学びました。
当日は当グループから2名がパネリストとして参加し、技術的な問題を中心に議論をおこないました。
この討論会を踏まえて、放射性廃棄物処分問題を国民的議論につなげるべく、技術的な問題も踏まえたうえで原子力政策を本音で討論するワークショップを現在企画中です。
処分地公募と平行して、国の安全規制側も処分地の選定要件の議論を進めています。
当グループは、現在のまま処分地選定が進むことには反対であるが、安全規制側にも目を光らせ圧力をかける必要から、2002年7月に原子力安全委員会特定放射性廃棄物処分安全調査会の「概要調査地区選定段階における環境要件の考え方について」報告書(案)に対して要望書を提出しました。
これは同案があまりにもおざなりなものであったためで、委員会から返答は得られなかったが、最終案は常識的なものに大幅変更されていました。
その他/備考
<strong>対外的な発表実績</strong>
2002年9月 パンフレット「埋め捨てにしていいの?原発のゴミ」
見開きイラスト8ページ
・知っていましたか?「放射能のゴミ」を埋め捨てにすることを
・処分場をつくるのも大変、ゴミを埋めるのも大変、元に戻すのも大変
・地下に埋めても安全なの?
・処分地が決まれば問題が解決するの?
解説2ページの計12ページのカラーパンフレット。
2002年9月 原子力産業新聞、ふぇみん、日本消費経済新聞、電気新聞
資源エネルギー庁と共同企画で開催し、パネリストとしても参加した公開討論会「どうする高レベル放射性廃棄物」の紹介記事
今後の展望
高レベル放射性廃棄物の問題は、かりに原発が明日すべて止まったとしても、何らかの判断と選択を迫られる問題です。
単に地下に埋める「地層処分」に反対を唱えるだけで、地上でどのような保管または管理をしていくのか、「地層処分」への批判と同様の厳しい批判にたえるものを作り出せなければ、反対の運動が社会全体から広く信頼を得ることは難しいと考えています。
そのために、地上に置くにしろ地下に置くにしろ、いかに「処分」が困難であり、「良い選択」はないということを提示して、原子力利用を見直すことにつながるように、技術的な問題について信頼される批判活動を着実に続けていきたい。
今年度は基金の助成により、これまで以上に原子力関係者と、原子力利用と廃棄物の問題を議論する機会を多く持ちました。
こうした経験をもとに、原子力をどうしていくのか、国民が主体的に議論し、決めていくことに資していく可能性もさぐっていきたい。
高木基金への意見
高木基金の助成により、充実した活動を続けることができました。
事務的な細かな点で気になったことはありますが、それは別にご連絡したいと思います。
公開プレゼンテーションは2回参加いたしましたが、刺激を受ける場であったと思います。
幸いにして、当グループは引き続いて2003年度も助成を受けることができました。
活動によっては、1年だけの短いスパンの助成は不十分なこともありえるという趣旨と理解いたしました。
このことを踏まえての総体的な意見は2年間の活動を通したうえで述べさせていただこうと思います。